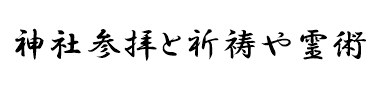パワースポットで有名な榛名神社に参拝し、本物の縁結びや祈願祈祷を実施。その効果も体感できました。
榛名神社(はるなじんじゃ)
群馬県高崎市の「榛名神社」
この地で有名なだけではなく、全国的に知られているパワースポット神社です。

赤城山と妙義山を含む「上毛三山(じょうもうさんざん)」の一つ、榛名山の中腹に鎮座しています。
山岳信仰の中心として、古来より民衆から広く崇められてきました。

鳥居をくぐり朱色の橋を渡った先にあるのは「随神門(ずいしんもん)」
神仏分離令発令前まで仁王門と称し、仁王像が安置されていました。
ここから本社まで約700mほど参道が続きます。
冬になるとマイナスまで気温が冷え込み雪景色になるため、雪の参道を歩く防寒や装備が必要です。

右側には川のせせらぎを奏でる榛名川。
手つかずの自然を四季の美しさを堪能でき、神聖な雰囲気が漂う参道が魅力的です。
参道を歩いて行くと毘沙門天をはじめ七福神の像が次々と現れ、参拝者を楽しませてくれます。

朱色の「みそぎ橋」を渡ると杉並木や苔むした石。
更には、ご神水が湧き出る「水琴窟(すいきんくつ)」や「廻運燈籠(かいうんとうろう)」があり。
四季折々楽しめる豊かな風景が訪れた参拝者を癒やしてくれます。

榛名川支流を引いて造られた「瓶子の滝(みすずのたき)」です。
瓶子とはお神酒を入れる器を指し、滝の両側にある岩を瓶子に見立て、この名が付けられたそうです。
当日は一部が氷結しており、幻想的な姿を見ることができました。
真冬になると滝が凍結するため氷瀑のシーンを期間限定で楽しめます。

参道から数段の石段をのぼると、左側に立つ高さ16mの三重塔。
天御中主神、高皇産霊神、神皇産霊神、伊弉諾神、伊弉冊神を祀っています。
このように榛名神社では、至る所で神仏習合の名残を見れる場所です。

参道は岩が張り出している所があり、補強や雪よけのためかトンネルになっていました。
トンネル内には、厄災と安全を祈願する「塞神社(さいのかみしゃ)」が祀られており。
塞神社には幸神信仰が残っているとされ、縁結びや子宝にご利益があるとされています。

鮮やかな朱塗りの手水舎。
ここから更に石階段を上って本殿を目指します。

石階段の中程、左側にあるのは「矢立杉(やたてすぎ)」と呼ばれる巨木。
武田信玄の逸話が残っており、箕輪城攻略の戦勝祈願し弓矢を立てたとされています。
近くに鎮座するのは1859年建立、国指定重要文化財の「神幸殿(みゆきでん)」です。

総欅造りの風格ある「双龍門(そうりゅうもん)」
この時は修復工事中でしたが、門の背後には迫力ある奇岩がそびえ立っています。
4枚の扉に龍の彫刻が施されていることから双龍門と呼ばれるようになりました。
1855年の竣工、国指定重要文化財です。

その先には1806年に再建された銅板葺きの拝殿があります。
ご祭神は、火の神「火産霊神(ほむすびのかみ)」と土の神「埴山毘売神(はにやまひめのかみ)」
火と土の神を祭っていることから、開運や商売繁盛、仕事運や金運アップのご利益が有名です。
拝殿の右側には、大きな杉と大国主命を祀る杵築社もあります。

技巧を凝らした彫刻が施されている見事な拝殿です。
拝殿から幣殿、本社へ繋がっています。

本殿は背後には、圧倒的迫力の「御姿岩(みすがたいわ)」
天に向かってそびえ立つ岩を見上げると上部に大麻がかけられています。
写真では伝わりにくいのですが、どのような方法で大麻をかけたのか驚嘆の光景です。
御姿岩の下部は洞窟になっており、そこにご祭神を祀っています。
当日は、他の参拝者の邪魔にならないよう配慮しながら祈祷を行いました。

木々や川、巨岩奇岩などあらゆる自然との融合で魅せる榛名神社。
人の手で作り出した歴史的建造物も圧巻です。