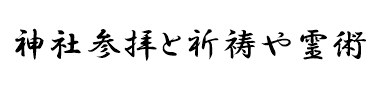パワースポットで有名な鵜戸神宮に参拝し、本物の縁結びや祈願祈祷を実施。その効果も体感できました。
鵜戸神宮(うどじんぐう)|洞窟内に鎮座する神秘的な聖地
宮崎県日南市の「鵜戸神宮」は、太平洋の日向灘(ひゅうがなだ)に面した洞窟内に鎮座する大変珍しいパワースポット神社です。長い年月をかけて波によって形成された天然洞窟と、朱塗りの重厚な社殿が融合する姿は「圧巻」の一言。見るものに自然の素晴らしさと、古来より育まれた日本固有の信仰心を肌で感じさせてくれます。
この神社は海外からも注目されており、平日でも国内外から多くの参拝者(旅行者)が訪れています。

ご祭神とご利益|日本神話に登場する神々
神社の主祭神は、初代天皇とされる神武天皇の父神「日子波瀲武鸕鷀草葺不合尊(ひこなぐさたけうが야ふきあえずのみこと)」。本殿にはさらに下記の五神(柱)が祀られています:
- 大日孁貴(おおひるめのむち) - 天照大御神の別名であり、太陽の神として知られる
- 天忍穂耳尊(あめのおしほみみのみこと) - 天照大御神の子であり、稲穂の神
- 彦火瓊々杵尊(ひこほのににぎのみこと) - 天孫降臨の主役であり、地上統治の神
- 彦火々出見尊(ひこほほでみのみこと) - 山幸彦として知られ、海と山の恵みの神
- 神日本磐余彦尊(かむやまといわれひこのみこと) - 神武天皇であり、日本の建国の神
山幸彦と海幸彦伝説の舞台
日本神話に登場する有名な神様がずらりと名を連ねていますが、鵜戸神宮は「山幸彦と海幸彦」伝説の舞台となった地。現在の本殿が鎮座する洞窟に、主祭神の母である豊玉姫命(とよたまひめのみこと)が出産する際に「産屋」が用意されたそうです。そして我が子の健やかな成長を願い、身体の一部を置いていったところが岩(お乳岩)となったと伝えられています。
今もお乳岩からはお乳水と呼ばれる水がしたたり落ち、伝説の息づきを感じることが出来ます。地元の人々からも「鵜戸さん」の愛称で親しまれ、縁結び、夫婦円満、安産、海上安全などのご利益があるとされています。
参拝ルートと建造物|朱色の楼門と神門
参拝に訪れたこの日は天候に恵まれ、青い空と眼下には日向灘が広がり、行く先々で朱色の建造物とのコントラストが色鮮やかでした。まず駐車場に面した鳥居をくぐり、砂利の敷き詰められた参道を進むと「神門」が現れます。
楼門の威風堂々たる姿
その先には「楼門」が構えていますが、あまりの威風堂々とした姿に、訪れた参拝者は皆しばらく足を止めて見上げていました。楼門は、二階部分の左側に「櫛磐窓神(くしいわまどのかみ)」、右側に「豊磐窓神(とよいわまどのかみ)」の御門神を祀る、「門守社」でもあります。そのため一礼してからくぐると良いでしょう。

鵜戸稲荷神社|商売繁盛のご利益
楼門から参道を歩いていくと、左側に幾重にも続く朱色の鳥居。階段を上り切った先に、末社の「鵜戸稲荷神社」が鎮座しています。社殿も色鮮やかな朱色で、ご祭神は商売繁盛にご利益がある「宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)」が祀られています。


千鳥橋と玉橋|日本三大下がり宮へのアプローチ
本殿までは二つの橋がありますが、一つ目の「千鳥橋」を渡ると、右側に白波が打ち寄せる日向灘がさらに広がります。たまたま巫女さんが渡るところを撮影させて頂きましたが、日本ならではの情緒ある写真に仕上がりました。

玉橋の特殊な建築技法
二つ目の「玉橋」は建築方法が特殊で、釘を全く使用せず橋板36枚から作られた反橋です。玉橋を渡り終えると、崖に沿って造られた石階段を下っていきます。このように鳥居より社殿が低い位置にある神社は「下り宮」と呼ばれており、群馬県の貫前神社(ぬきさきじんじゃ)、熊本県の草部吉見神社(くさかべよしみじんじゃ)と並び、鵜戸神宮は「日本三大下がり宮」に選ばれています。

洞窟内の本殿|天然の聖域と八棟造り
洞窟の手前にある鳥居をくぐると本殿が現れます。長い年月をかけ、波によって削られてできた天然洞窟の広さは約1千平方メートル(約300坪)。その中に厳かに佇む朱塗りの社殿は、拝殿・幣殿・本殿が一体となった八棟造。
歴史的な創建と改修
創建は第十代崇神天皇の御代と伝えられ、延暦元年の再興から改築と改修を繰り返し、昭和43年には257年ぶりの改築が行われました。豊玉姫命の産屋があったとされる洞窟内は、自然の生気と古代からの信仰心が調和した神聖なエネルギーが感じられます。
祈祷の実施|霊力伝心と開運術
当日この神社で行ったのは「霊力伝心」と「開運術」の2つですが、そのご利益が働くようしっかり実施しました。それだけでは御座いません。必ず最後に祈祷を行いますので、勿論この神社でも拝殿前で祈祷を行っています。

摂末社とお乳水のご利益
洞窟内には摂末社も鎮座していますので、社殿を一周しながら参拝ができます。ちなみに、本殿の横にあるのは神武天皇の兄神でもある彦五瀬命(ひこいつせのみこと)を祀る「皇子神社」。その隣には神直毘神を含む9柱の神様を祀る「九柱神社(ここのはしらじんじゃ)」が鎮座し、厄災除けや海上安全などにご利益があると言われています。
さらに本殿の後方には、先程ご紹介した安産にご利益があるお乳水がしたたり落ち、その場で頂くこともできます。また、お乳水を練って作った「おちちあめ」は戦前からある伝統の授与品。ほんのり甘い味が口当たり良く、妊婦さんが舐めると母乳の出が良くなると言われており、お土産としても人気があるようです。
亀石の伝説|願いが叶う運試しスポット
そして鵜戸神宮のもう一つの名物となるのが、洞窟下の磯にある亀の形をした「亀石」。豊玉姫が乗ってきた亀が岩になったと伝えられ、亀石の背中には窪みがあります。
運玉投げの願掛け
男性は左手、女性は右手で願い事してから運玉を投げ,亀石の窪みに入ると願いが叶うと言われる人気の運試しスポットです。意外と難しくなかなか窪みに収まりません。当日もたくさんの人がチャレンジをしていましが、大半の人達は外れていました。その中で皆様の願いが叶うようにと私が投げてみたところ、見事窪みの中に運玉が収まりました。子供のように嬉しくなったことを今でも思い出します。

アクセス情報と周辺施設
鵜戸神宮までのアクセスは車か、宮崎駅からバスに乗車するのが一般的です。到着まで時間がかかりますが、それだけの価値を十分に感じさせてくれるパワースポット。参道にはおしゃれなカフェが並んでいますので一息つきながら、神話の世界と鵜戸崎の魅力を楽しんで下さい。
おすすめの参拝プラン
- 午前中に鵜戸神宮を参拝(混雑を避けるため)
- 楼門や千鳥橋で写真撮影
- 洞窟内の本殿で祈祷と参拝
- お乳水で安産祈願
- 亀石で運試しに挑戦
- 参道のカフェで休憩
- おちちあめをお土産に購入
周辺観光のおすすめ
鵜戸神宮周辺には他にも見所がたくさんあります。日南海岸のドライブや、サンメッセ日南のモアイ像、饅頭屋さんの郷土菓子など、宮崎ならではの体験が楽しめます。ぜひ一日かけてゆっくりと宮崎の自然と文化を満喫してください。
鵜戸神宮は自然の神秘と古代からの信仰が融合した、他にはない特別なパワースポットです。縁結びや安産を願う方はもちろん、日本の神話や歴史に興味がある方にもおすすめの場所です。機会があれば、ぜひ足を運んでみてください。